こんにちは、あくあ園長です。
2025年7月、京都府宇治市の市立保育所で、給食時に1歳の園児たちに対して、保育士が「泣かんとごっくんし」「飲み込んで」などの大声で暴言を吐き続けたという痛ましい事件が報道されました。
今回は、まず事実を整理し、そのうえで「なぜ給食で不適切保育が起きるのか」、そして現場で何ができるかという解決策まで、具体的に解説していきます。
1. 事件の概要:何が起きたの?
まずは今回の出来事について、あらためて確認しておきましょう。どんな場面で、どんな対応が問題視されたのかを正しく知ることが、保育士としての学びにもつながります。
京都府宇治市の市立保育園で、50代女性保育士が2024年~2025年にかけて以下の不適切な対応を行い、減給処分(10分の1を1ヶ月)を受けました。
- 泣いて給食を食べない1歳児に対し、「泣いてもあかん」「飲み込んで」と強い口調で叱責
- 泣き止まない子どもを廊下に1人で残す
- 子どもの腕を引っ張り、椅子から転倒させる行為もあった
市は「心理的虐待」および不適切保育とし、市長も再発防止を表明しています。
2. なぜこうした事件が起きたのか? プロの視点で考察
「どうしてこんなことが起きてしまったのか?」——きっと多くの人が感じたと思います。
でもこれは、ひとりの保育士だけの問題ではありません。現場に立つ者としてわかる、“本当の原因”を深堀りしてみましょう。
🧠 ① 保育士の「メンタル疲労」と「孤立感」
- 長時間・多役割をこなす中で心身の余裕が奪われ、短気になったり子どもを対処対象とだけ見る心境に陥りやすい
- 時に「自分が正しく、子どもは甘えている」と思ってしまい、暴言や力を使う行為に至ることも
🛡 ② 組織の仕組み・仕切りがなかった
とくに市立園などでは、保育士が限られた人数で業務を回すことも多く、バックアップ体制が十分に整っていない場合もあります。そんななかでは、困っていても誰にも頼れず、“一人で抱え込む保育士”が生まれやすくなるのです。
- 複数保育士による給食のローテーションが不在だった
- 問題行動の初期段階での共有・カバー体制が不十分で孤独感が蓄積された可能性も
🎓 ③ 保育教育の「育成不足」
新人保育士だけでなく、ベテランであっても「自分のやり方が本当に正しいのか」を見直す機会がなければ、保育観がアップデートされません。今回のようなケースは、まさに“教育の空白”が浮き彫りになった例だといえるでしょう。
- 新人やベテランに関わらず、「対応のプロとしての実践力」が園内で共有されていないと、適切な対応が遅れる
- 特に1歳児の「食べ渋る・泣く=成長過程の自然な反応」の理解と対処教育が不足していた可能性
🔍 結論:事件は「個人の問題」でありつつも、それ以上に、メンタル・現場の仕組み・教育体制の三重苦が重なった結果だと考えます。
3. 給食で不適切保育が起こる構造的背景とは?
ここからは、より具体的に「なぜ給食の時間帯に、こうした不適切な関わりが起こりやすいのか?」という点を見ていきましょう。
実は給食って、保育士にとっても子どもにとっても、なかなかの“ハードタイム”なんです。
📌 理由①:「時間に追われる給食スケジュール」
スケジュールをこなさないといけない、という心理的な焦りは、ときに保育者に強い不安感を与えてしまうものです…。
- 一斉給食は時間管理が厳しく、“遅れると次の活動に支障”というプレッシャー
- 遅れると、子どもを急かす・叱るなど不適切対応を誘発する環境です
📌 理由②:「心理的支援の知識が未浸透」
子どもが食べないとき、あなたならどう声をかけますか? 「食べなさい!」と怒るのではなく、“心を動かす関わり方”が求められます。でも、そのスキルを学ぶ機会がなかったり、現場でのロールモデルが不在だと、つい短絡的な言葉に頼ってしまうのです。
- 食べ渋る子に対し、励まし・遊び・スキンシップ等で誘導するスキルより、「叱る」対処が先になってしまう
- 必要なのは心理的安心を与える声かけ・関わり方なのに…実践が伴わないと暴言につながりやすいです
📌 理由③:「園の人材・育成体制が不十分」
人手不足の園では、若手が孤立してしまいがちです。「困っているときに誰かに相談できる」という当たり前が、職場にない保育士さんも少なくありません。
不適切保育の背景には、こうした“育たない職場環境”があるケースが多いのです。
- 居眠り・ミス・不適切対応が連鎖的に起こる
- 定期的な研修や振り返りがないまま仕事を回すと、問題行動が蓄積・放置される可能性が高まります
4. 解決策:個人・園・制度レベルでできること
このような理由があることはわかりましたが、しかしながら、断じて、不適切保育をしていいということではありません。
大事なことは、「では、どうすれば防げるか?」を考えることです。ここからは“3つのレベル”で考えられる改善策をご紹介します。
事件をきっかけに、保育現場がより安全でやさしくなるには、ひとりひとりの意識と、周囲のサポートが欠かせません。
✅ 個人レベル:保育士として成長を続ける
- セルフケア(早寝・リフレッシュ・休息)を習慣化
- ケース別「食べ渋る子への対応」研修受講(心理的支援を重視)
- 日誌や振り返りに「うまくいった声かけ」「次回の改善点」を書く習慣を導入
✅ 園レベル:環境と育成体制を整える
働く現場の雰囲気やチームワークが整っていれば、保育士も安心して業務に向き合えますよね。
人間関係や時間の使い方を見直すことで、不適切保育の“芽”は早い段階で摘み取ることができます。
- 給食の時間を柔軟にとるスケジュール再設計
- チーム保育・メンタルサポート・事例共有の場を定期開催
- 研修や“ケーススタディ”で、言葉・行動の影響を全員で学ぶ機会を設ける
✅ 制度・自治体レベル:仕組みの整備
自治体や運営法人にできることも、たくさんあります。
保育士が「相談しやすい」「休みやすい」「声を上げられる」しくみを作ることで、同じような事件の再発を防ぐことができます。
- 市立園は定期監査・事例レビューの強化
- 保育所での不適切行動予防プログラム導入
- 保育士が安心して相談・休めるメンタル窓口の設置
5. それでも“働きづらさ”を感じたら転職も選択肢です
ここまで対策をご紹介してきましたが、「やっぱり今の園では難しそう…」と感じる保育士さんもいらっしゃるかもしれません。
無理をして我慢し続けるより、もっと自分らしく働ける場所を探すことも、大切な選択肢です。
そんな方には、よく「“転職”も手段のひとつです」とお伝えさせていただいています。保育士専門の転職エージェントに相談し、あなたにぴったりの園で働いてみませんか?
🔹 保育士専門転職エージェントで得られるサポート
- 園の体制(研修・メンタルケア・チーム育成)や人間関係の実態を、登録アドバイザーが詳しく教えてくれます
- 一人で情報収集せずに、効率的に“自分に合った園”を見つけられます
- 求人調整や見学アレンジ、条件交渉も代行してくれるので、今すぐ転職しなくても安心です♪
▶ まずは無料で相談してみましょう
🧡 最後に
子どもが泣くのは、成長のあかし。
給食を食べないのは、自分のペースで学んでいる証。
それを「甘え」と判断し、大声や暴力で解決としてしまう対応が、今回の事件につながった。
どうか保育の現場に戻ったとき、
「子どもの声を聴く」「自分の心をいたわる」「制度に頼る」
そんな在り方が、あたりまえの選択肢になってほしいと願っています。
あなたが安心して、自分と子どもを大切にしながら働ける場所が見つかりますように。

元保育園園長&保育士のあくあです|保育士10年→転職して園長に|プロの視点で、子育てのヒント、保育業界の裏話、保育士の転職アドバイスをシェア|質問・相談、面接練習、フォロー大歓迎!

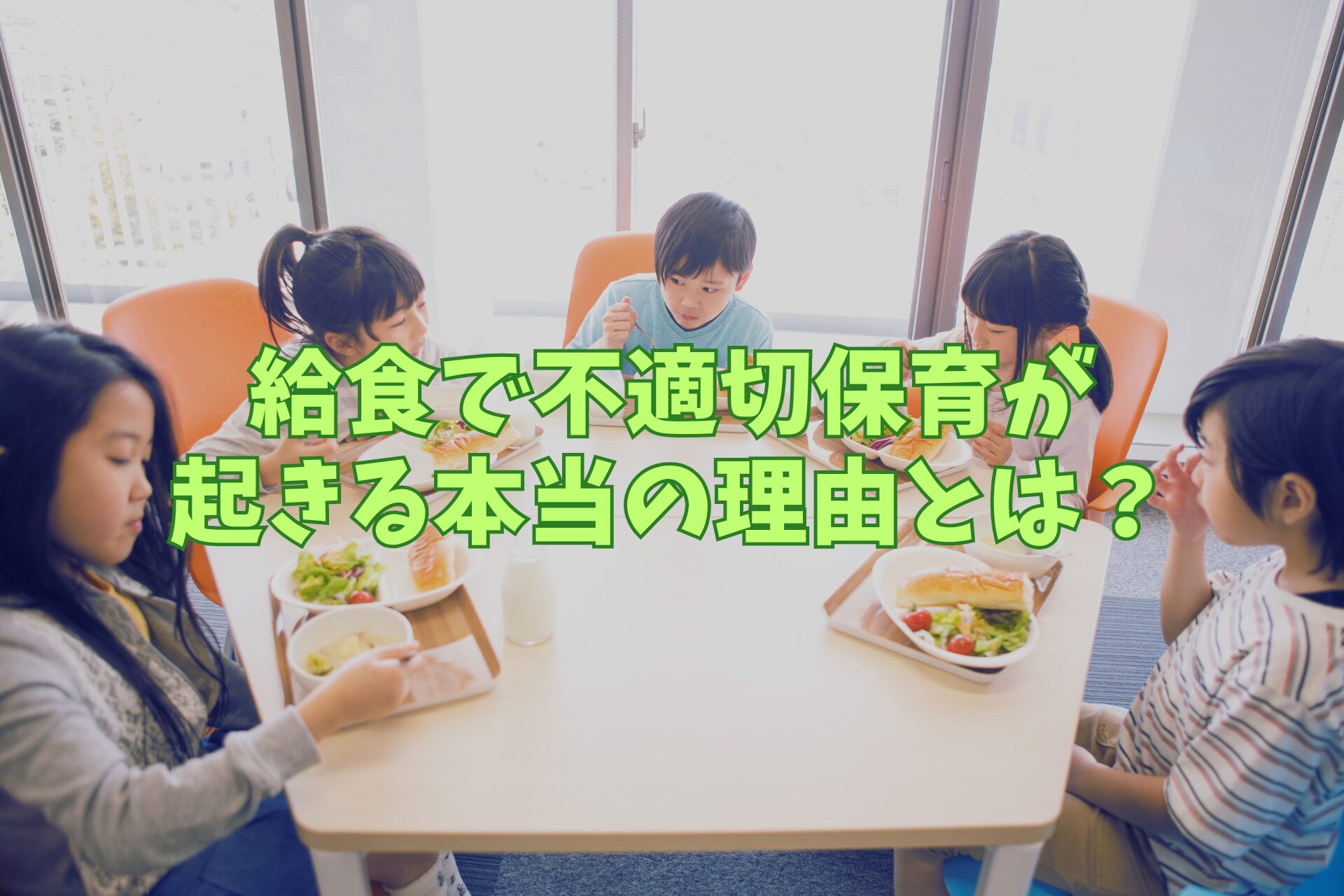


コメント